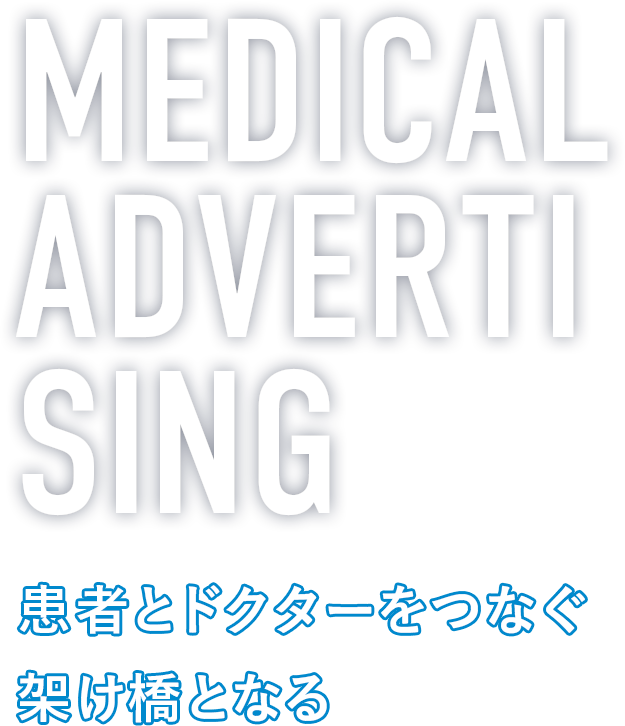TOPICSRecent
EventsWhat's Happening These Days.新着情報
OUR SERVICEBRIDGE OF MEDICAL“Change Healthcare through the Power of Advertising.”広告のチカラで、医療の課題を解決する架け橋をかける。


01SERVICEIRYOTO医療機関向け広告
「IRYOTO(イリョウト)」は、ホームページ/求人ホームページ/ランディングページ/印刷物による広告の企画提案を行っています。


02SERVICEManaging Advertising広告運用
| 01 | Google、Yahooのリスティング広告を企画提案・運用します。 |
|---|---|
| 02 | SNS広告等を活用し、患者さんの来院数増加を企画提案、運用します。 |




PHILOSOPHYCORPORATE PHILOSOPHY提供するサービスで、必ず成果を出し続けるために。
私たち株式会社ドクターブリッジのスタッフは、患者さんと医師の架け橋となるために「提供するホームページによる広告企画で必ず成果を出すこと」を徹底しております。そのために医療機関で提供される診療・治療内容をしっかりと理解し、患者さんに分かりやすく伝えることを心がけています。これらを実現するための弊社企業理念をご紹介いたします。

Mission目的・使命
| 01 | 病気で悩む患者さんとドクターをつなぐ架け橋となる |
|---|---|
| 02 | 人生100年時代を自分らしく健康で生きていけるように情報発信する |

Vision目標・将来性
日本の超高齢化社会の問題解決に貢献していく
病気や症状で悩む方々が早期に治療を受けることで、健康を維持できるようにインターネット上に役立つ情報を発信していく。弊社の医院・クリニックのホームページによる広告の企画提案サービスは、そのために実施していきます。
また、病気や症状を認識してから治療や改善を行っていくのではなく、定期的に受ける健康診断等で、生活習慣病のリスクや突発的な病気を予防する習慣を持てるように、食事や運動に関する情報を発信していきます。
そうすることで微力ながら、60歳以上の方々が社会活動を引退するのではなく、継続していただくことで医療費削減、60歳以降も納税していただき、若年層、中年層の負担を少しでも軽減し、次の世代に健全な世の中をつないでいきます。

Values行動方針・価値観
弊社が企画・運営を行い発信する情報は
ユーザー中心の、ユーザーにとって価値あるコンテンツを第一に考えて提供しています。
これまで20年、ホームページによる広告企画に携わってきた中で感じてきたのは、企業側が業績向上を意識するあまり、納品や売上を優先してサービスを提供してしてしまい、品質が低下していくホームページを多数見てきました。
弊社では、ユーザーにとって役立つ情報を提供していくことを優先することで、徐々に企業成長していく行動指針をスタッフ一同に共有しております。
そうすることで、医療・健康に関する情報発信のマーケットリーダーになることを目指します。特に、医療機関のホームページによる広告企画では、『失敗しないホームページによる広告』を達成していきます。
RECRUIT求人情報

CONTENTS
01. RECRUITInterviews with Staffスタッフインタビュー

CONTENTS
02. RECRUITSchedule of the Day1日のスケジュール

CONTENTS
03. RECRUITSocial Programme福利厚生と数字でみるドクターブリッジ
ENTRYJOIN TO DR.BRIDGE !
COMPANY PROFILEWe Are
DoctorDR.BridgeBridge Between Patients and Doctors.会社概要
| 社名 | 株式会社ドクターブリッジ |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-4-9 テアトル神南オフィス棟4FGoogle Map |
| TEL | 03-6427-9941 |
| FAX | 03-6427-9942 |
| 設立年月日 | 2015年7月23日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 上田 英之 |
| 事業内容 | 集患支援事業 / メディア運営事業 / WEBコンサルティング事業 / 広告代理店事業 / イマカラ(管理栄養士による健康メディア) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 / みずほ銀行 渋谷中央支店 / りそな銀行 虎ノ門支店 / 楽天銀行 第二営業支店 |
| 顧問税理士 | 渋谷税理士法人 |
ACCESSOur Officeアクセス方法
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-4-9 テアトル神南オフィス棟4F |
|---|---|
| 最寄り駅 | ・JR/私鉄各線「渋谷駅」から徒歩8分 ・JR「原宿駅」、千代田線「明治神宮前」から徒歩7分 |
CONTACTPlease Contact Here!
サービスのご依頼や
お問い合わせはこちらから